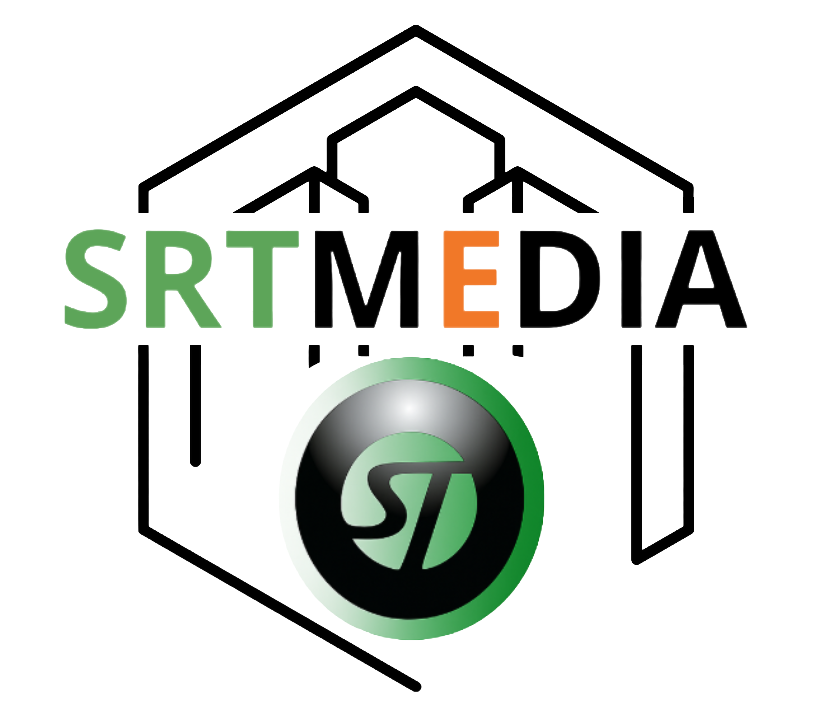快適で暮らしやすい住まいづくりはSRTコーポレーションにお任せ。
豊富なリフォーム・リノベーション実績を活かし、キッチンや浴室など設備の変更まで、
ライフスタイルに合わせた空間設計をご提案します。
オーナー様には資産価値向上を、入居者様には理想の住まいをご提供。
「まずは相談したい」「見積もりだけでも知りたい」という方も大歓迎です。
【リフォーム】施工不良の見極め方と対処法を徹底解説

リフォーム施工不良は「完成後」ではなく「途中」で見極める
リフォームの施工不良は、完成後に突然発覚するものではありません。多くの場合、契約前・工事中・引き渡し前のいずれかで兆候が出ています。問題は、それを判断材料として認識できていないことにあります。
「仕上がりが少し雑に見える」「説明と現場の進み方が違う」といった違和感は、後から大きな不具合につながるケースが少なくありません。
施工不良を見極める判断軸は3つしかない
① 契約内容と現場のズレがあるか
施工不良の多くは、設計図・見積書・説明内容と実際の工事内容が一致していないことから始まります。材料のグレード変更、工程の省略、説明のない仕様変更があれば要注意です。
条件によっては問題にならない場合もありますが、事前説明がない変更は施工品質以前のリスク要因です。
② 工程管理が曖昧になっていないか
工事の進捗説明が「だいたい」「問題ありません」と抽象的になってきた場合、管理が弱くなっている可能性があります。工程表が形骸化している現場では、仕上がり精度が落ちやすくなります。
③ 不具合への反応が遅い・軽い
指摘に対して即座に現地確認が行われない、原因説明が曖昧なまま進行する場合は注意が必要です。技術的な問題よりも、対応姿勢そのものが施工不良の予兆になります。
この条件なら問題になりにくい/なりやすいの分岐
この条件なら致命的な施工不良になりにくい
- 契約書・仕様書が詳細に整理されている
- 変更点が都度書面で共有されている
- 現場責任者が一貫して同じ
この条件が重なると施工不良リスクが高い
- 口頭説明が多く書面が少ない
- 着工後に仕様が頻繁に変わる
- 下請け任せで管理者が見えない
特に後者が重なる場合、完成後に不具合が顕在化しやすくなります。
よくある誤解「見た目がきれい=施工不良ではない」
施工不良は必ずしも外観に現れるとは限りません。防水処理、下地処理、固定方法などは完成後に見えなくなります。
施工不良か判断が分かれやすいグレーゾーン事例
実務相談で特に多いのが、「不満はあるが施工不良と言い切れるのか分からない」というケースです。
以下は判断を誤りやすい代表例です。
| 状況 | 施工不良になりやすい条件 | 問題になりにくい条件 |
|---|---|---|
| クロスの継ぎ目が目立つ | 事前説明なく仕上がり基準を下回る | 事前に仕上がり許容範囲の説明がある |
| 建具の建て付けが甘い | 調整依頼に応じない・再発する | 微調整で改善し再発しない |
| 床鳴りがする | 下地処理不足が原因 | 構造上避けられない軽微な音 |
このように「症状」だけで判断すると誤解しやすく、原因・説明・是正対応まで含めて見る必要があります。
業者側・管理側から見た「問題が起きやすい施主行動」
管理側の立場では、次のような状況が重なるとトラブルが起きやすくなります。
- 判断をすべて業者任せにしている
- 疑問点をその場で確認しない
- 完成を急ぎすぎる
これは施主の責任という意味ではなく、確認機会が減ることで不具合が見逃されやすくなるという構造的な問題です。
施工不良を「証拠が残るうち」に判断する重要性
引き渡し後に不具合が発覚すると、原因特定や責任範囲の整理が難しくなります。工事中であれば写真・工程・材料の確認が可能です。
実際に進める前に、第三者相談窓口や判断基準を整理しておくと安心です。
リフォーム施工不良の見極め方は「正解探し」ではない
施工不良を完全に予測することはできません。しかし、「この条件なら危ない」「ここで確認すべき」という回避判断は可能です。
完成後の評価ではなく、途中段階での違和感に気づけるかどうかが、施工不良を防ぐ最大の分かれ道になります。