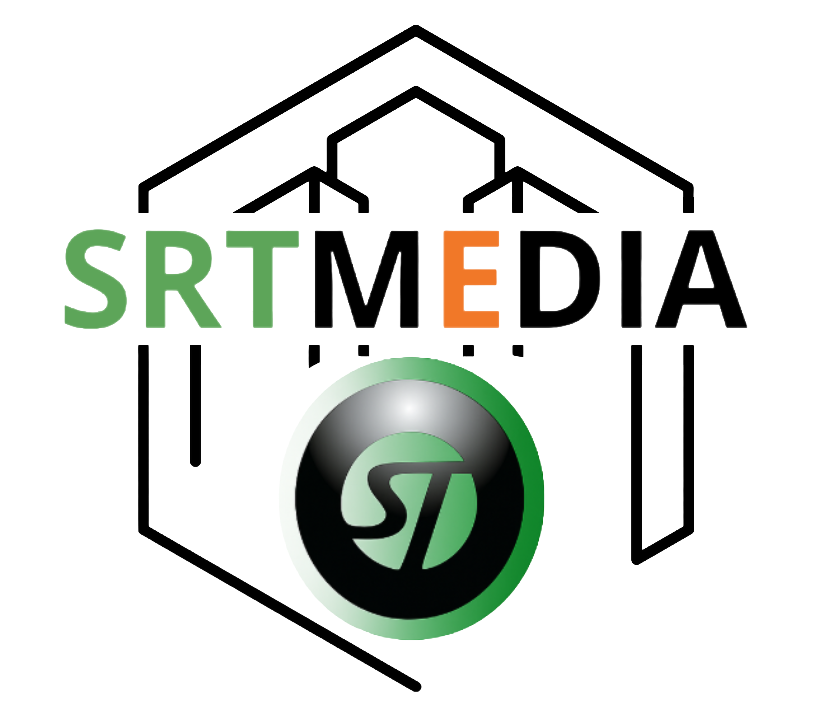快適で暮らしやすい住まいづくりはSRTコーポレーションにお任せ。
豊富なリフォーム・リノベーション実績を活かし、キッチンや浴室など設備の変更まで、
ライフスタイルに合わせた空間設計をご提案します。
オーナー様には資産価値向上を、入居者様には理想の住まいをご提供。
「まずは相談したい」「見積もりだけでも知りたい」という方も大歓迎です。
リフォーム後に固定資産税が上がる?税金対策を解説

リフォームを考えている方は、夢の住まいを手に入れるための第一歩を踏み出そうとしていることでしょう。しかし、リフォーム後に待ち受ける意外な現実があるのをご存知ですか?それは、リフォームによって固定資産税が上がる可能性があるということです。この税金の仕組みや、どのように影響を受けるのか、さらにはその対策について知識を深めておくことが重要です。
この記事では、リフォームを行った際の固定資産税の変動について詳しく解説し、リフォームを計画する上での留意点や、税金対策の方法をお伝えします。夢の住まいを手に入れるために必要な知識を身につけ、安心してリフォームを進めていきましょう。
リフォーム後の固定資産税の変動について
リフォーム後の固定資産税の変動は、用途変更がある場合に顕著です。例えば、自宅の一部を事務所や店舗にする場合、用途変更を伴うリフォームでは固定資産税が上がることがあります。用途が変わればその部分の評価額も変動し、固定資産税の算出基準である固定資産評価額が上がる可能性があります。したがって、リフォーム計画を立てる際には、税金の変動についても考慮する必要があります。
リフォームが固定資産税に与える影響とは?
住宅のリフォームを行う際、大多数の場合は固定資産税に直接の影響はありませんが、大規模なリフォームや増築を伴う場合は、翌年度以降の固定資産税が上がる可能性があります。例えば、リノベーション済みの中古住宅を購入するケースでも、工事の内容によっては固定資産税が高くなっていることがあります。リフォームによる税金の増加は計画段階で確認しておくとよいでしょう。
固定資産税が上がる具体的なリフォームのケース
自宅の一部を事務所や店舗にするなど、用途変更を伴うリフォームでは固定資産税が上昇します。用途が変わることでその部分の評価額も変動し、固定資産税の算出基準である固定資産評価額が上がる可能性があります。このため、リノベーションなどで活用する部分の用途に関しては慎重な計画が必要です。
固定資産税が変わらないリフォームの条件
フルリフォームなどの大規模なリフォームでない限り、「建築確認申請」は必要ないため、固定資産税に影響することはありません。つまり、土地の用途が変わらない限り、リフォームによって固定資産税に影響することはないと言えるでしょう。このことから、税金を気にせずに行えるリフォームもあります。
リフォームに関連する税金対策と控除方法
リフォームに関連する税金対策として、個人が自ら住まわれている住宅に対して特定のリフォームを行った場合、所定の条件を満たすことで所得税の税額控除を受ける可能性があります。具体的には、耐震、省エネ、介護対応など特定のリフォームを行った際に、税の控除や減額により費用負担を軽減できる制度が整備されています。たとえば、特定の条件を満たすバリアフリーリフォームを行った場合、10年間にわたり最大140万円の控除を受けることが可能です。このように、税金対策をしっかりと行うことで、リフォームの負担を大幅に抑えることができるのです。
リフォームで受けられる税金控除の種類
リフォームにおいて受けられる税金控除には、主に耐震、バリアフリー、省エネ、同居、長期優良住宅化、子育て対応の6種類があります。それぞれの工事の控除率は対象工事費の10%で設定されています。たとえば、耐震リフォームの場合、対象工事費が限度額を超過した場合でも、1000万円までの範囲で5%の控除が認められます。これにより、リフォームに伴う負担を大幅に軽減することが可能です。
補助金を活用してリフォームをお得に行う方法
リフォームをお得に行う方法の一つとして、補助金や助成金の活用があります。補助金を申請することで、工事費用の一部を国や地方自治体から支援してもらうことができます。たとえば、バリアフリー工事の場合、最大20万円の補助金が適用されることがあります。補助金制度は年によって条件が変わるため、事前に最新の情報をリフォーム店や自治体のホームページで確認することが重要です。このように、補助金制度をうまく活用することで、リフォームにかかる費用を大幅に抑えつつ、理想の住環境を実現することができます。
リフォーム計画時の固定資産税再評価の必要性
多くのリフォーム工事では固定資産税に影響することはありません。建築確認申請が伴う場合は増額しますが、耐震・断熱・バリアフリーなど要件を満たせば減税対象となることがあります。例えば、住宅を耐震化するためにリノベーションを実施した場合、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額される可能性があります。このため、リフォームの内容によっては、再評価後に税額が増減する場合があります。新たに評価された建物に基づいて固定資産税が計算されるため、工事内容の把握が重要です。
固定資産税の再評価が必要な場面とは?
固定資産税の再評価が必要な場面は、建築確認申請が必要な増築や改装の場合に多く見られます。例えば、住宅を店舗や事務所に改装した場合、内装仕様や耐久性の基準が変わり、固定資産税が増減することがあります。このため、評価額は構造や用途ごとに基準が定められており、特に市町村においては再評価が必要と判断される場合があります。再建築価格に基づき評価されるため、適切な評価額が求められます。
再評価を避けるためのリフォームのポイント
再評価を避けるためには、まずはしっかりと予算を立てることが重要です。例えば、間取り変更がない場合は、基本的に固定資産税への影響はないと考えられます。間取りや床面積を維持した部分的なリフォームを選択し、間取りの大きな変更を控えることが再評価を避けるポイントです。また、信頼できるリフォーム業者を選んで、契約書にはリフォームの具体的な内容や材料、施工期間が明記されているか確認しましょう。これにより、大きな改装を避け、再評価のリスクを軽減することが可能です。
まとめ
リフォームを行うことで、物件の価値が上がることが多く、その結果として固定資産税が増加する可能性があります。これは特に大規模なリフォームや、家の広さを増やすような工事を行った場合に顕著です。したがって、リフォームを計画する際には、その後の税負担についても考慮することが重要です。
税金対策としては、リフォームに関する費用を事前に計算し、どの程度の負担が予想されるかを把握しておくことが役立ちます。また、適用可能な減税制度や特例を活用することで、税負担を軽減できる場合もあります。具体的な対策を講じることで、リフォームに伴う税金の影響を最小限に抑えることができます。